都会でよくみるカラスですが、カラスがどのような生活をしているか、その生態について詳しく知っている人は少ないでしょう。
カラスの生態がわかると退治する際の参考にもなるので、生態を知ることは重要です。
こちらの記事ではカラスの生態や習性などについて詳しく説明し、具体的な被害や対策の注意点、おすすめの撃退方法について解説します。
カラスの生態を理解して被害に合わないようにしたい方は、ぜひ参考にしてください。
カラスの生態や習性とは?種類や巣の特徴、活動時期など解説

カラスの生態について、習性や種類、巣の特徴、食べ物や繁殖期などそれぞれ詳しく解説します。どのような生態をしているか知ることはカラスの被害を防ぐ対策にもつながるので、まずはカラスの生態をよく知りましょう。
カラスの生態:特徴・習性など解説
カラスは黒い体の色をしているイメージが強い鳥類ですが、羽は紫・藍色といった光沢を持っています。体の大きさは種類によっても異なりますが全長は50~60cm程度、体重は300~700g程度です。
非常に賢い鳥類として知られており、たとえば信号機の意味を理解したり人の顔を覚えたりすることができます。また光り物を集める習性があるのも有名です。カラスの対策方法にはさまざまなものがありますが、このように賢い生き物であるため安易な対策では効果を発揮しにくいことがわかるでしょう。
カラスの種類
本にはさまざまな種類のカラスがいますが、主に以下ような種類のカラスがいます。
・ハシブトガラス
・ハシボソガラス
・コクマルガラス
・ミヤマガラス
・ワタリガラス
・ホシガラス・カチガラス
上記の種類のうちでも特に日本に多く生息しているのが、ハシブトガラスとハシボソガラスの2種。ハシブトガラスは太いくちばしを持ち体が黒色をしたカラスであり、湾曲した上くちばしを持つという特徴があります。
ハシボソガラスもハシブトガラスと同じく全身が黒色をしており、ハシブトガラスよりも細くまっすぐなくちばしをしています。
カラスの巣の特徴
カラスは3~4月くらいの時期につがいを作り繁殖期に入るため、この時期から巣作りも始めます。高い樹木などに営巣することが多いですが都会にいるカラスは電柱などに営巣することもあり、その場合には建物の隙間など人目に付きにくい場所を選んで営巣します。
カラスは巣の材料として針金ハンガーを使うことでよく知られており、ベランダに掛けてあるハンガーを持っていって巣の材料に使うこともあるので注意しましょう。また巣の内側には動物の毛やビニール袋などを使い、最終的にはお椀型に巣を作ります。
カラスの食べ物
カラスは雑食性であり、植物の種子や昆虫類、農作物などの果実といったように、なんでも餌として食べることができます。そのほか鳥の卵やヒナに動物の死体、残飯なども食べることができ、都会にいるカラスはゴミを荒らして残飯を餌とすることも。
カラスは鳥類のなかでも非常に賢い鳥であり、餌をとったら物陰にかくしておいてあとから食べる、固いものはわざと車に踏ませてから食べるといったように、食べ物をとるためにさまざまな工夫をします。
カラスの繁殖期や活動時期
カラスの繁殖期は3~7月ですが、時期ごとに習慣の特徴があります。
まず3~4月の時期はオスとメスがつがいをつくって行動し、オスがメスに対して餌を運ぶ求愛給餌が見られます。またこの時期に巣材を集めて巣作りもスタート。4~5月になると3~5個ほどの卵を産んで、卵がかえるまでの20日間ほど卵を温めます。
そして5~6月に孵化して子育てが始まり、そこから1カ月ほどで雛が巣立ちします。はじめは親鳥に餌をとってもらいながら集団内で仲間と生活しますが、やがて独立して自分で餌をとれるようになり、集団の中でともに生活するようになります。
生息地や活動場所
生息地は種類によっても異なりますが、ハシブトガラス・ハシボソガラスの2種は全国的に広く生息しており特にハシブトガラスは日本でもっともよくみかけるカラスです。ハシブトガラスはもともと森や山に生息していた鳥ですが近年では都会へも住むようにになり、ビルを樹林のようのに見立てて生活し、都会でも繁殖して個体数を増やしています。
ほかにもハシボソガラスは農耕地や河川敷といった開けた場所を好んで生息する特性があり、冬鳥のミヤマガラスは都心や農耕地、森に河原とさまざまな場所で活動します。このように同じカラスでも種類によって行動範囲が異なるのです。
カラスみたいな鳥との違いは?
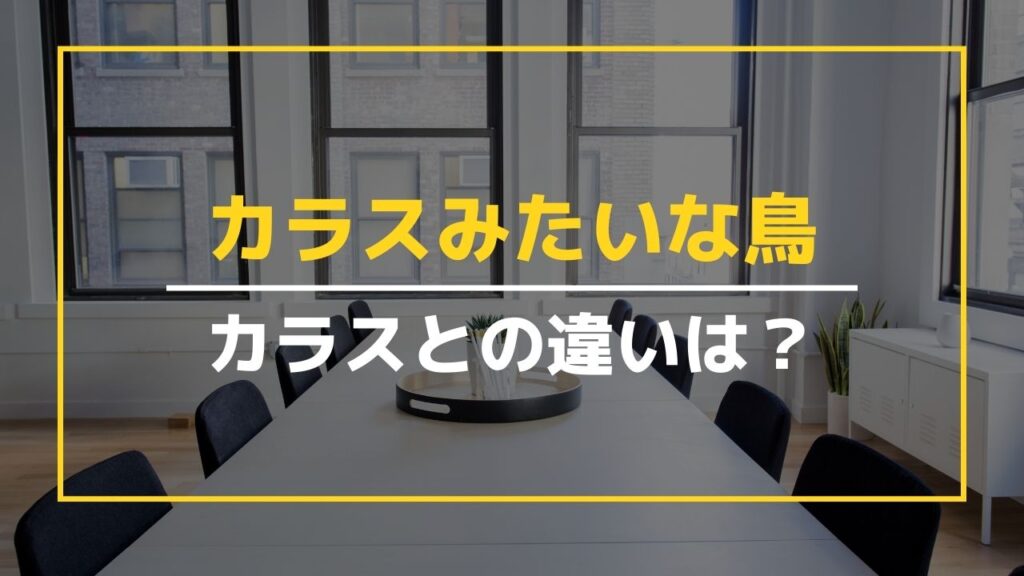
カラスみたいな鳥は日本に数種類いますが、そのうちの何種類かの鳥を紹介します。
・クロサギ
・カラスバト
・クロツグミ
・オオバン
クロサギはサギの仲間であり、黒い体をしたカラスみたいな鳥ですが、カラスと比べて足や首が長く足が黄色のも特徴の一つでしょう。体の色が黒いためカラスみたいな鳥といえますが、姿形が違うため見分けることができ、生息地も水辺であるため都会でみることは多くありません。
カラスバトはハトの仲間ですが体が黒く、こちらもカラスみたいな鳥といえます。ハトはカラスよりも頭部やくちばしが小さいため、こちらも見分けることが可能です。
カラスによる4つの被害を紹介
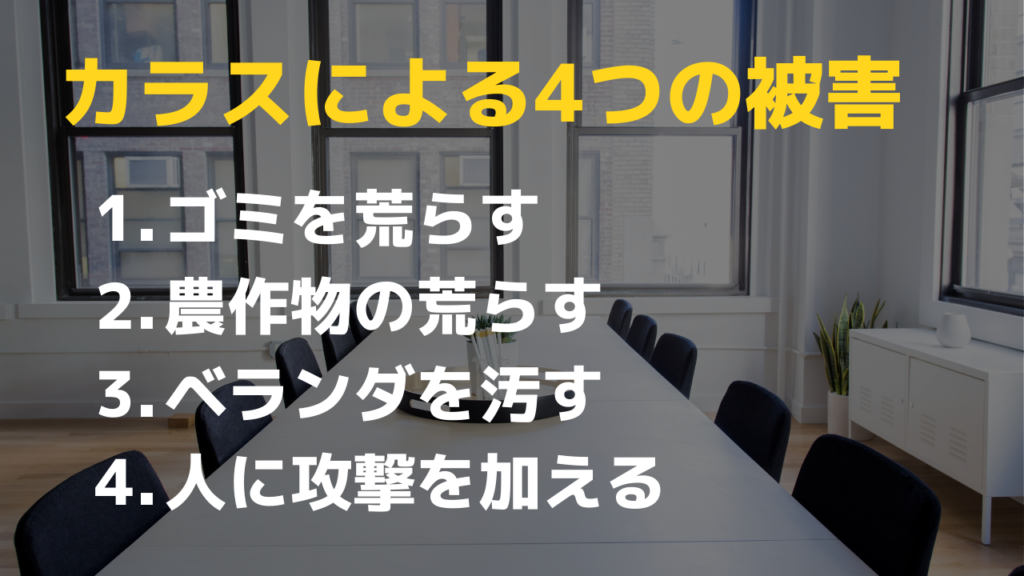
カラスはさまざまな被害をもたらしますが、特に多いな被害をあげると以下のとおりです。
・ゴミを荒らす
・農作物の荒らす
・ベランダを汚す
・人に攻撃を加える
被害に合った対策がとれるよう、それぞれ具体的にどんな被害をもたらすのかを解説します。
カラス被害1.ゴミを荒らす
カラスは雑食であるためが出した生ごみなどから餌を探し外に放置しておいたゴミを荒らします。収集日に出したごみが回収されるまでの間にカラスに荒らされ、路上にゴミが散乱している様子をみたことがある方も多いでしょう。
カラスは視力が発達しているため、赤やオレンジなど果物の色に似たものを識別してゴミを荒らしていると言われています。
カラス被害2.農作物を荒らす
カラスによる農作物の被害は深刻であり、トマトやスイカ、キャベツなどさまざまな農作物を食べられ多くの畑で食害にあっています。まだ収穫期にないような野菜や果物でも突いて穴を空けたりするため、食べる目的だけではなくいたずらのような感覚で畑を荒らすこともあります。
カラスの被害は食害に限らないので、まだ収穫期にない畑の農作物であっても油断できません。
カラス被害3.ベランダを汚す
カラスがベランダに来るとフンをしていくことがあるので、ベランダがフンで汚されてしまいます。カラスのフンは不衛生であるのはもちろんのこと、臭いもするので不快感も強いでしょう。
またカラスのフンには病原菌が含まれているため、乾いて風に舞ったふんを吸い込んでしまうと感染症を引き起こす危険もあります。
カラス被害4.人に攻撃を加える
カラスは都会にいる鳥類のなかでは比較的大きいため、攻撃されると怪我をする可能性があります。
カラスは臆病で警戒心の強い生き物なので、基本的には人を襲いません。しかし子育て中は卵やヒナを守るために攻撃的になるので、うかつに近づくと襲われる可能性があります。そのため3~4月の子育て時期には特に注意しなければなりません。
自分でできるカラス対策!注意点についても紹介

カラス対策で重要なのはまず、カラスを寄せつけない環境を作ることです。カラスのとまる木を剪定したり生ごみをできるだけ出さないなどの対策をすることでカラスが近寄りにくくなるでしょう。
撃退策としては忌避剤を使用する、音や光を使う、テグス・ワイヤーを張るといった方法があります。防鳥ネットを使えば物理的に侵入を防げるため、範囲が広くなければすべて覆ってしまうのがもっとも有効です。
注意点としては、自分でできる対策はカラスを追い払うことのみで駆除はできないということです。カラスの駆除には狩猟免許が必要であり、勝手に駆除することは法律によって禁止されています。
法律違反の場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるので注意してください。
カラス駆除は業者に依頼するのがおすすめ!

カラスは鳥獣保護法によって保護されている鳥なので、自分で駆除したり罠を使って捕獲するには役所の許可が必要です。しかし狩猟免許を持った業者であればカラスの駆除・捕獲ができるので、自分での対策が困難であれば業者への依頼を検討しましょう。
業者に依頼すれば手間をかけずに駆除でき、カラスの生態を知り尽くしたうえでその生態や被害状況に適した駆除を実施してくれるため、より高い効果があるでしょう。
さらにアフターフォローがついている業者であれば、万が一被害が再発した場合も再駆除を依頼できるのでより安心感があるでしょう。
業者の選び方やおすすめ業者を知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

まとめ
カラスには多くの種類がありますが、都会で見る機会が一番多いのはハシブトガラスでしょう。都会にいるカラスは巣作りの際にベランダにあるハンガーなどを持って行って巣の材料にすることがあるので注意してください。
カラスは賢い鳥であるため被害に合った場合の対策が難しく、繁殖期になると攻撃的になることもあるため駆除の際は注意しなければなりません。自分での駆除が難しいと感じたら業者に依頼することもできるので、カラスの生態を理解したうえで自分なりに対策を考えましょう。

